LLMOとは?SEOとの違いやメリット、実施方法、注意点を紹介
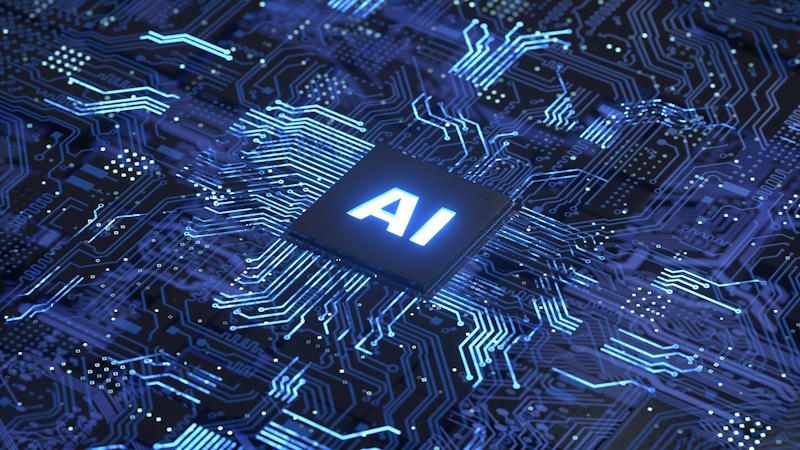
「最近、AIで検索するユーザーが増えているからか、自社サイトのアクセスが減ってきた」「検索結果の上部にAIの回答が表示されることで、検索流入が減るのでは?」といった不安を感じてはいませんか?
従来のSEO対策では、検索結果で上位に表示されることが目的でしたが、生成AIが検索結果にも活用されている現在では、「AIに選ばれる情報源」として自社サイトを最適化することが重要になっています。
このような新しい考え方は「LLMO(大規模言語モデル最適化)」と呼ばれ、LLMOを自社サイトに取り入れることで、検索順位に依存せず、AI経由で見込み客にリーチできるようになります。
この記事では、以下の内容をわかりやすくご紹介します。
・LLMOの基本概念とSEOとの違い
・実施メリット
・AIに引用されるためのページ構成や文章の書き方、技術的な対応方法
・効果測定の方法
また、株式会社クリエイティブバンクのWeb集客サービス「バンソウ」では、「AI時代のSEOやLLMOを始めたい」「AI検索に対応したい」という企業様向けに、無料相談を受け付けています。
まずは以下のボタンからサービス内容をご確認ください。
執筆者

マーケティングサポート「バンソウ」のメディア管理人
株式会社クリエイティブバンクのマーケティングサポート「バンソウ」のメディア管理人。得意分野は、SEO全般・サイト分析・オウンドメディア・コンテンツマーケティング。バンソウはクライアント様のBtoBマーケティングをサポートするサービスです。詳しい内容はこちらをご覧ください。
AIや検索エンジンに評価されるには?
バンソウでは、検索エンジンから評価されるためのSEO対策はもちろん、
AIに評価されるコンテンツを提供するためのLLMOもサポートしています。
「SEOだけでなくLLMOも強化したい」という方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
LLMOとは
LLMO(Large Language Model Optimization、大規模言語モデル最適化)とは、ChatGPTやGeminiといった大規模言語モデル(LLM)を用いた生成AIが回答や検索結果を表示する際に、自社のコンテンツが引用されたり、自社の社名・ブランド名が言及されたりすることを目的として、サイト内のコンテンツやサイト構造を最適化する方法を指します。
LLMOによって自社コンテンツがAIに引用・参照されることによって、通常の検索結果への露出だけでなく、AIを経由した露出機会が増えるため、より多くのユーザーに自社を認知してもらえたり、自社サイトへのアクセスを増加させたりできるといった効果が期待できます。
なお、業界では、AIO(Artificial Intelligence Optimization)やGEO(Generative Engine Optimization)といった名称が使われることがありますが、どちらもLLMOとほぼ同じ意味で使われており、生成AIの生成結果に対する自社サイトの最適化を目的としています。
LLMについては、以下の記事で詳しくご紹介しています。
LLMOが注目されている理由
LLMOは、生成AIの進化やユーザーの検索傾向の変化、検索エンジン上での検索結果の変化などにより、AIに自社の情報を引用・参照してもらうことの重要性が高まっていることが主な理由として考えられます。具体的には、次のとおりです。
AIの進化により検索結果が変化している
現在はChatGPTやGemini、Microsoft Copilot など、大規模言語モデルを用いたさまざまな生成AIが登場しており、業務や日常生活でもこれらのAIを活用する機会は多いでしょう。
最近では、このような生成AIが検索エンジンにも取り入れられており、検索結果に集められた内容の概要として、検索結果の上部にAIによる要約文が表示されることがあります。
例えば、以下はGoogleで「LLMOとは」と検索した歳の検索結果の上部です。

このように、検索結果に表示されたコンテンツの内容の要約を表示することで、ユーザーは複数のサイトを開き内容を確認せずとも、すぐに知りたい情報を手に入れられるようになります。
AIによる要約は、Yahoo!や Microsoft Bing といったGoogle以外の検索エンジンでも、検索結果の上部に表示されます。
【Yahoo!の場合】

【Microsoft Bing の場合】

上記のように、どの検索エンジンにおいても、検索結果の上部は広告枠とAIによる要約で占められており、掲載順位が1位のページでも、スクロールして画面下部に移動しなければ確認しづらくなっています。
また、ChatGPTなどのAIとチャットでやりとりをする中でも、Web上のページから情報を引用されることがあるため、検索エンジンを通さずとも、AI経由で自社のページに訪れてもらえる機会も増えています。

引用:ChatGPT
このような検索結果の変化により、AIの要約文に引用・参照されやすいコンテンツづくりが重要になっています。
AIに選んでもらえる情報源の価値が高まっている
上記のように、AIを活用した検索結果が上部に表示されるようになったり、AIとのやり取りの中でWeb上のページ内容を引用されるようになったりしたことから、AIに選んでもらえる情報源の価値が高まっています。
さらに、ただ質の高い情報を発信するだけでなく、「AIに理解してもらえるか」「引用しやすいコンテンツになっているか」も新たな価値として重要視されています。
そのため、SEOで重要であった「ユーザーにとって価値のある質の高い情報を発信する」だけでなく、ユーザーとAIのどちらにとっても有用性の高いコンテンツが重視されるようになったことから、LLMOに力を入れる企業が増えています。
特に、SEOでも重要な要素であるE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)は、AIが情報の一貫性や出典元の信頼性などを理解するうえでも必要となるため、AIの理解を促すためにもより一層E-E-A-Tを強化することがLLMOでは必須となるでしょう。
検索結果の変化によるクリック率低下が懸念される
検索結果の表示内容が変化し、これまで上位表示されていたページが検索結果の下部に表示されてしまうことによるクリック率の低下も懸念されています。
SEOツールを提供しているAhrefsの調査によると、300,000個のキーワードで調査した際に、AIによる要約が表示されているものはされていないものに比べて、上位ページのクリック率(CTR)が34.5%低下することが明らかになりました。
参照:AI Overviews Reduce Clicks by 34.5%|Ahrefs
そのため、これまではSEO対策のみを行い上位表示されていたページは、AIに引用・参照されなければユーザーにクリックしてもらいづらくなり、上位表示の効果を得られなくなります。
また、同じくAhrefsの調査によると、3,000サイトのトラフィックデータを分析した際に、63%のサイトがAI経由から1回は訪問されていることがわかりました。
参照:63% のサイトが AI 経由のトラフィックを確認。3,000 サイトの調査から見えた事実|Ahrefs
今後は「上位表示された自社のページをクリックしてもらう」だけでなく、「AIによって引用された自社のページをクリックしてもらう」ことも視野に入れ、自社のコンテンツをユーザーの目につきやすい位置に表示できるよう、SEOだけでなくLLMOにも力を入れることが重要視されています。
LLMOとSEOの違い
上記では、SEOだけでなくLLMOにも取り組むことも重要である旨を述べましたが、LLMOとSEOの具体的な違いについてあいまいな方も多いでしょう。
LLMOとSEOは、どちらも自社サイトのコンテンツやページ構造などを最適化するWebマーケティング施策の一つです。
ただし、LLMOは、AI(LLM)が自社のコンテンツを理解し、生成結果に引用・参照してもらうことを目的として行われる、AIを対象とした施策です。一方で、SEOは検索エンジンに自社のコンテンツを正しく伝え、検索結果の上位に自社のコンテンツを表示させることを目的として行われ、検索エンジンを対象としています。
LLMOとSEOの主な違いは、次のとおりです。
|
LLMO |
SEO |
|
|
目的 |
AIの生成内容での自社コンテンツの引用・参照・言及 |
検索結果への上位表示、自然検索による自社コンテンツへの誘導 |
|
対象 |
LLM |
検索エンジン |
|
成果とする指標 |
AIの引用回数、表示内容 |
検索順位、自社コンテンツへのトラフィック数やPV数、クリック率 |
|
重視される要素 |
内容のわかりやすさ、簡潔さ、正確性 |
E-E-A-T、被リンクによる信頼性、コンテンツの質 |
SEOを適切に行うことでLLMO効果も高まる
上記のとおり、LLMOとSEOは目的や対象が異なる施策で、SEOを行いつつLLMOにも力を入れることが今後は重要とされるものの、適切なSEOを行い有益な情報を提供していれば、自然とLLMO効果も高まります。
GoogleのDanny Sullivan(ダニー・サリヴァン)氏は、SEOもLLMOも本質は変わらないとし、「良いSEOは良いLLMO」であり、これまでSEOで行ってきたことは今後も継続し、ユーザーを第一に考えた有益なコンテンツを提供することが重要であると述べています。
参照:WordCamp US - Danny Sullivan "How (and why!) Google Search Keeps Evolving"|WordPress(YouTube)
そのため、「SEOとあわせてLLMOを行わなければならないがリソースが足りない」「LLMOに取り組む時間がない」と慌てず、まずは自社のSEO状況を見直し、不足している要素があれば改善することから始めるのがおすすめです。
当社では、貴社のSEO状況を簡単に可視化できるSEO無料診断サービスを提供しています。診断結果は1~2営業日でお届けし、その後の営業行為なども一切行いません。少しでも興味のある方は、ぜひ以下のボタンから詳細をご確認ください。
LLMの仕組み
上記では、LLMOの概要についてご紹介しました。LLMOは大規模言語モデルであるLLMを対象に自社のコンテンツやページ構造を最適化しますが、そもそもLLMはどのように情報を理解し、生成するのでしょうか。
以下では、LLMの仕組みについてご紹介します。
生成AI(LLM)が情報を生成・引用する仕組み
LLMは、蓄積された学習データをもとに、プロンプト(指示文)に対する最適な内容を生成します。
Webデータの収集サービスを提供するOxylabsによると、LLMの学習データには、Webデータや学術論文、Wikipedia、ニュースメディア、コードソース、動画プラットフォームなどの情報が含まれています。そのため、さまざまな情報源の中から信頼できる情報を学習し、生成内容を検討しているといえるでしょう。
参照:LLM Training Data: The 8 Main Public Data Sources|Oxylabs
また、Google検索における生成AI機能「AI Mode」では、「query fan-out(クエリ・ファンアウト)」という技術が採用されています。
クエリ・ファンアウトは、ユーザーが検索したトピックだけでなく、そのトピックに関連する情報やデータソースを含めて複数の関連検索を行う技術です。
例えば、ユーザーが「Web集客」と検索した際、GoogleのAI機能はWeb集客だけでなく、「SEO」「コンテンツマーケティング」「リスティング広告」「インフルエンサーマーケティング」などさまざまな関連情報をあわせて検索して情報を収集します。
これにより、ユーザーが求める情報に加えて、あわせて知りたい情報などの補足コンテンツも素早く検索できるようになりました。
見出し構造やテキストをわかりやすく整理することで適切に認識もらいやすい
Googleでは、クエリ・ファンアウトとあわせて、「Thematic Search(テーマ別検索)」という技術も採用しています。
クエリ・ファンアウトと内容に大きな差はなく、ユーザーが検索した情報をAIが生成する際には、テーマ別に関連する情報を網羅する技術です。
このようにテーマ別に情報を整理する際には、ページのメタデータ(ページタイトルやメタディスクリプション)、HTML構造、テキストなどを参照します。そのため、H2・H3といった見出し構造やテキストはAIが理解しやすいようわかりやすく整理することが、LLMOにおいて重要といえます。
参照:Google’s Query Fan-Out Patent: Thematic Search|Search Engine Journal
LLMの仕組みについては、以下の記事でもご紹介しているため、あわせてご覧ください。
LLMOを実施するメリット
上記では、LLMOの概要やLLMの仕組みをご紹介しました。LLMOに取り組み、実際にAIに自社のコンテンツや会社名・ブランド名などを引用・言及してもらえることによって、以下のようなメリットが得られます。
検索上位に表示されていなくてもユーザーに気づいてもらえる
これまでのSEO対策では、コンテンツの質やサイト自体の評価(サイトパワー)が検索結果のランキングを左右しており、SEO対策を実施していてもなかなか上位に自社のコンテンツが表示されないケースも多くありました。
しかし、LLMOに取り組むことで、検索結果の上位にランクインしていなかったとしても、AIに自社のコンテンツを引用してもらえる可能性があります。
AIによる要約は上位表示されたコンテンツよりも上部に表示されるため、AIによって引用や言及がされていれば、検索結果の上位表示ができていなかったとしてもユーザーに自社を認知してもらえたり、サイトへアクセスしてもらえたりすることが期待できます。
競合性の高いキーワードでも上位表示を狙いやすい
上記のとおり、LLMOに取り組み、AIに自社コンテンツが引用・言及されることによって、検索結果の上部に自社のコンテンツや社名・ブランド名などが表示されます。
これにより、競合性の高いビッグキーワードでも、サイトパワーが強い競合サイトを抑えて上位に表示される可能性があります。特に、自社独自の情報やオリジナルコンテンツ、外部サイトから引用されやすい独自の調査データなどをコンテンツに含めることで、AIからの引用を狙いやすくなるでしょう。
自社への信頼性やブランド価値を高められる
上記で触れたとおり、AIによる引用・言及によって、検索結果の上部に自社のコンテンツが表示されることで、自社への認知度を高めやすくなります。
また、AIという第三者が情報を引用することによって、ユーザーが「AIが引用する信頼性の高い情報である」という信頼感や、「AIが引用した情報を自分の目で確かめたい」という興味を抱かせられるでしょう。
LLMOの実施方法:コンテンツ制作面
ここまで、LLMOに取り組むメリットをご紹介しました。LLMOを実際に行う際は、コンテンツ面とテクニカル面での両方で工夫をする必要があります。ここからは、LLMOの実施方法をご紹介します。
まず、コンテンツ制作面で押さえておくべきポイントは、以下のとおりです。テクニカル面ではHTMLなど専門知識が問われる場面も多いため、ITに関する知識に自信がない方や、すぐに着手できるものから取り組みたい方は、コンテンツの見直しから始めましょう。
AIが理解しやすい構成を意識する
LLMは文脈や単語の前後での関係性などを読み取りながら文章を認識できるものの、人間ではないため複雑な記事構成になっていることで、誤認する可能性もあります。そのため、まずはユーザーやAIが理解しやすい構成を、以下に沿って意識しましょう。
論理的な構成になっているか確認する
AIに文章構成を正しく伝えるためには、「起承転結」や「ピラミッド構造」を意識するとよいでしょう。
|
構成の型 |
内容 |
|
起承転結 |
|
|
ピラミッド構造 |
|
このように、作成するテーマに沿って適した型を選ぶのがおすすめです。また、構成に沿って文章を作成する際は、各パートの内容も加味しながら、前後のパートとのずれが生じないよう意識しながらまとめましょう。
必要な話題を取捨選択しながら網羅する
記事構成を作成する際は、テーマに沿って必要となる話題を網羅することで、コンテンツの信頼性が増します。
例えば、「BtoBマーケティング」について述べる場合は、BtoBマーケティング全体の話題に触れたうえで、以下のような話題も盛り込むとよいでしょう。
- リードジェネレーション
- リードナーチャリング
- MAツールの活用方法
- SEO対策の重要性
- 営業部門との連携のコツ
- KPI・ROIの設定方法
しかし、さまざまな情報を盛り込みすぎることで、本来のテーマから逸脱してしまい、記事内で何を伝えたいのかがあいまいになってしまうことから、LLMOに正しくコンテンツの内容を理解してもらえない可能性があります。
記事構成を検討する際は、テーマに沿った内容は何かも考慮しながら、必要な話題を取捨選択しつつ網羅しましょう。
1つの見出しごとに問いと答えを用意する
AIはユーザーの検索(問い)に対して回答をするかたちで情報をまとめるため、問いと答えを意識した構成を組み立てることで、AIから引用されやすくなります。
例えば、「BtoBマーケティング」について述べる場合は、以下のような見出しと本文の構成があげられます。
→本文では、BtoBマーケティングとは何かを説明(答え)
H2:BtoBマーケティングはどのように進めるの?(問い)
→BtoBマーケティングを行う流れを説明(答え)
H2:BtoBマーケティングでよく使われる施策は?(問い)
→BtoBマーケティングの主な施策を紹介(答え)
H2:BtoBマーケティング今後どうなる?(問い)
→BtoBマーケティングの最新情報や今後の傾向を説明(答え)
このように、問いとなる要素をH2に設定し、答えとなる要素をH3、H3の補足としてH4…というように見出しを組み立てることで、ユーザー・AI双方にとって理解しやすい構成となります。
AIに採用される情報を掲載する
AIに自社のコンテンツを引用してもらうためには、信頼性の高い情報を発信する必要があります。信頼性の高い情報を掲載するためには、以下のポイントを押さえておきましょう。
自社で調査・入手した情報を掲載する
信頼性の高い情報を発信するためには、自社で調査・入手した一次情報をコンテンツに含めるのがおすすめです。対策キーワードに関連するデータやアンケート結果などを掲載することで、AIからも引用してもらいやすくなります。なお、オリジナルのコンテンツはSEO対策においても評価されやすい傾向にあります。
一次情報を発信する際は、以下のような情報を含めるのがおすすめです。
- 自社で検証・実験したデータ
- 自社開発のツールやサービスを用いた調査データ
- 自社で実施したアンケート結果
- 自社で実施した専門家へのインタビュー
E-E-A-Tを意識する
AIに信頼されやすい情報を発信するためには、「LLMOが注目されている理由」でも触れたように、E-E-A-Tを意識することが大切です。E-E-A-Tは、Googleが各ページを評価するうえでも重要な指標としており、それぞれの要素において、以下のような内容を重視しています。
- E(Experience、経験):実体験、体験談、顧客の声、導入事例
- E(Expertise、専門性):著者・監修者情報、コンテンツの専門性の高さ
- A(Authoritativeness、権威性):会社概要、外部からの評価(被リンク、サイテーション)
- T(Trustworthiness、信頼性):運営者情報、プライバシーポリシー、利用規約、サイトのSSL化
これらの内容がコンテンツに含まれており、内容も充実していることで、検索エンジンやAIから高く評価されやすいコンテンツを作成できます。 E-E-A-Tについては、Googleでも詳細に説明しているため、あわせてご確認ください。
参照:E-E-A-T と品質評価ガイドラインについて|Google 検索セントラル
参照:検索品質評価ガイドライン:概要|Google
情報を引用する場合は出典元を明記する
コンテンツを充実させる際には、自社独自の情報だけでなく、外部サイトからの情報(文章や画像、動画など)を引用・参照したい場合もあるでしょう。このとき、ただ情報を載せるだけでなく、出典元も明記することで、「信頼できる情報を引用している」と評価されます。
特に、外部サイトの情報を引用する際は、個人が運営するブログやSNSからではなく、公的機関(省庁、自治体など)・専門機関のサイトや、それらに所属する人物のSNSといった権威性の高い情報源から引用することで、信頼性の高い情報を掲載できます。
なお、外部サイトの情報を引用する際は、各サイトで引用ルールを設けている場合もあるため、基本的にはサイトごとのルールに基づいて記載しましょう。他者が作成した文章や画像などの著作物を、出典元を明記せずそのままコピー&ペーストして発信することは著作権の侵害にあたる可能性もあるため、注意が必要です。
画像の引用元の書き方については、以下の記事でもご紹介しています。
AIが読み取りやすい文章を作成する
記事構成やコンテンツに含める情報を踏まえて、AIに引用されやすい文章を作成する際は、結論から述べて伝えたいことを明確にしたり、箇条書き・番号つきリストなどを活用してわかりやすくまとめたりすることが大切です。
結論から述べる
AIが読み取りやすい文章を作成する際は、「結論ファースト」を意識しましょう。「AIが理解しやすい構成を意識する」のピラミッド構造でもあげたように、結論を述べた後にその背景や理由、補足情報などを含めることで、自身が文章の中で伝えたいことをわかりやすく明示できます。
また、結論から述べるかたちで文章を作成することで、AIにとっても内容を認識しやすくなり、主張を正しく把握できるため、引用・言及されやすくなります。
そのため、新規で作成する記事でこのような書き方を意識するのはもちろん、既存記事に対して、各見出しごとの文章構成を結論から始める書き方に修正したり、記事全体の主張を記事の導入文(リード文)に書き加えたりしてリライトするのもよいでしょう。
箇条書きや番号つきリストを活用する
AIに理解してもらいやすい文章を目指す際は、箇条書き・番号つきリストを活用するのもおすすめです。このような装飾で文章を整理することで、AIが項目ごとの内容を正しく把握しやすくなります。
なお、箇条書き・番号つきリストは、AIだけでなく人間の読者にとっても視覚的にわかりやすくなるため、ユーザーの利便性を考慮する面でも有効です。
例えば、以下のようにまとめるとよいでしょう。
- 情報の構造が明確になる
複数の要素を並べて整理できるため、AIが各項目を理解しやすくなります。
- 要点を短時間で把握できる
単なる長文よりも視認性が高くなるため、読者が離脱せずに内容を理解しやすくなります。
- ユーザーの利便性が向上する
スマートフォンなどの小さな画面でも読みやすく、直感的に理解できます。
定義文やQ&A形式での書き方を取り入れる
AIに引用してもらいやすい文章を作成する際は、定義文やQ&A形式の文章構造を意識するのもおすすめです。
定義文は、「AとはBである」「CはDやEという強みがある」「EはGに使われる」など、主語・述語のつながりが明確な文章を指します。このような定義文は主張がわかりやすく、AIにとっても内容を理解しやすい文章であるため、引用・言及されることが期待できます。
Q&A形式は、「Q.なぜ〇〇は△△なのですか?」「A.〇〇は▢▢という特徴を持つからです」といったように、質問と回答をQ&Aで簡潔にまとめた文章を指します。
Q&Aで説明することで、質問と回答をAIが認識しやすくなるため、検索結果上部の引用だけでなく、以下のような「関連する質問」で抜粋してもらえる可能性があります。

LLMOの実施方法:テクニカル面
ここまで、LLMOの実施方法におけるコンテンツ面でのポイントをご紹介しました。コンテンツをAIが理解しやすいよう整えることに加えて、LLMOではHTML構造やページ速度の改善といったテクニカル面でも最適化することで、AIに自社のページを認識してもらいやすくなります。LLMOを実施する際のテクニカル面でのポイントは、以下のとおりです。
正しいHTML構造でページを作成する
「LLMの仕組み」でもあげたように、AIはページタイトルなどのメタデータを参照します。見出しタグがばらばらに組み立てられていたり、必要な要素が含まれていなかったりするなど、ページのHTML構造が整っていない場合、AIがページ内容を正しく認識できず、自社の情報を引用してもらえない可能性があります。
HTML構造を整える際は、以下の点を確認しましょう。
- titleタグやmeta descriptionタグが設定されているか
- 見出しタグが適切に使用できているか
(H1タグは1ページに1つのみ使用しているか、H2タグの配下にH3タグ、H3タグの配下にH4タグ…の階層が組めているか)
- HTMLタグを正しい用途で使用できているか
(リストはul、olタグ、引用はblockquoteタグ、本文テキストはpタグなど)
- 画像にalt属性を設定できているか
HTML構造が適切に設計されていることで、検索エンジンもページ内容を正しく理解できることから、SEO評価も高まりやすくなります。コンテンツ作成を行う際は、このようなHTMLタグの設定を直感的に行えるCMSを利用するのもよいでしょう。
構造化マークアップを行う
構造化マークアップとは、ページ内の文章などに意味を持たせるために、HTMLに特定の情報を記述する手法を指します。構造化マークアップを行うことで、検索エンジンやAIは「これは〇〇の話だ」「この単語は企業名だ」と理解しやすくなります。
LLMOでは、主に以下の要素に構造化マークアップを行うとよいでしょう。
- 組織(Organization)
- 記事(Article、NewsArticle、BlogPosting)
- よくある質問(FAQPage、Question、Answer)
参照:組織(Organization)の構造化データ|Google 検索セントラル
参照:記事(Article、NewsArticle、BlogPosting)の構造化データ|Google 検索セントラル
参照:よくある質問(FAQPage、Question、Answer)の構造化データ
構造化マークアップは、LLMOだけでなく、SEOやMEO(マップエンジン最適化)にも有効な手法なため、専門的な知識やスキルが必要にはなるものの、Webサイト運用において対応しておくことをおすすめします。
なお、Googleでは構造化マークアップをサポートするヘルプページやツールなどを公開しています。構造化マークアップを行う際は、これらも参考に進めるとよいでしょう。
参照:Google 検索における構造化データのマークアップの概要|Google 検索セントラル
参照:構造化データ マークアップ支援ツール|Google
構造化マークアップについては、以下の記事でも詳しくご紹介しています。
ページの表示速度を最適化する
LLMOでは、ページの表示速度を改善し、スムーズにページを閲覧できる状態にすることが大切です。ページの表示速度が遅く、画像などの読み込みに時間がかかった場合、AIがページ内容をうまく読み取れず、情報を引用してもらえない可能性があります。
Googleでは、自社サイトのページ速度を確認できる無料ツール「PageSpeed Insights」を提供しています。PageSpeed Insightsでは、モバイル・デスクトップそれぞれでのページ速度を可視化できるだけでなく、具体的な改善点や改善後に期待できるページスピードも示してもらえる点が特長です。
参照:PageSpeed Insights
llms.txtを設置する
LLMOを行う際は、「llms.txt」というプロトコルを設置するのも一つの施策としてあげられます。llms.txtは、LLMのクローラー(Webページの情報を読み取るロボット)に対してクロールの許可や制御を行う役割を持っており、SEOにおいては「robots.txt」という検索エンジンのクローラーを誘導するプロトコルを使用することも多いです。
llms.txtは、以下のようにMarkdown形式で記述します。
# 株式会社クリエイティブバンク(バンソウ)
> 株式会社クリエイティブバンクは、法人向けにSEO・リスティング広告・
MEO・Web集客コンサルティングを提供するデジタルマーケティング企業です。
> 自社サービス「バンソウ」を通じて、BtoB企業・店舗・スクールなど幅広い業種のWeb集客を支援しています。
## 1. サービス案内
### トップページ: 集客を複合的に伴走支援|バンソウ
- **対象ページURL:** https://www.sales-dx.jp/
- **概要:** 株式会社クリエイティブバンクが提供する「バンソウ」は、SEO、リスティング広告、
MEO、SNS運用などを通じて、成果に直結するWeb集客支援を行う伴走型マーケティングサービスです。
---
## 2. バンソウの主なサービス
### SEOコンサルティング: SEOコンサルティング|バンソウ by 株式会社クリエイティブバンク
- **対象ページURL:** https://www.sales-dx.jp/service/seo-consulting
- **概要:** バンソウのSEOコンサルティングでは、キーワード設計から競合分析、コンテンツ戦略までを一貫して支援。
中長期的な自然検索からの集客を実現します。
---
### Web集客コンサルティング: Web集客コンサルティング |バンソウ by 株式会社クリエイティブバンク
- **対象ページURL:** https://www.sales-dx.jp/service/web-traffic-consulting/
- **概要:** SEO・広告・SNSを横断的に分析し、
企業の現状に合わせたWeb集客戦略を設計。成果が出るまで継続的に伴走支援します。
---
作成したllms.txtは、Webサイトのルートディレクトリ内に設置します。
外部サイトからの被リンクやサイテーションを獲得する
LLMOでは、外部サイトからの被リンクやサイテーション(言及)を獲得することでも、サイト自体の信頼性が増すため、自社の情報を引用・言及してもらいやすくなります。
このような外部サイトからの被リンクやサイテーションは、SEOにおいても外部対策と呼ばれており、自社サイトの検索順位やサイト評価を高める点でも重要です。
被リンクやサイテーションは基本的に自社でコントロールできないため、外部サイトで思わずリンクを張りたくなるようなコンテンツをこまめに提供し続けることが主に必要ですが、企業SNSアカウントでの発信やプレスリリース配信、メディアへの寄稿などでも被リンク・サイテーションの効果を高められます。
なお、自社で実店舗を運営している場合は、自社サイトで掲載している店舗情報と、SNSなどサイト外で公開されている店舗情報(NAP情報:Name(店舗名)、Address(住所)、 Phone number(電話番号))に相違がないかも確認しておきましょう。
目的別のLLMOの実施例
ここまで、LLMOの実施方法を、コンテンツ面・テクニカル面に分けてご紹介しました。実際にLLMOを行う際は、実施目的によっても取り組む施策が異なります。目的別のLLMOの実施例は、以下のとおりです。
自社コンテンツをAIに引用してもらう場合
自社コンテンツをAIに引用してもらう場合は、SEO対策に加えてAIに正しく情報を理解してもらえるよう働きかけることが重要です。
|
カテゴリ |
実施内容 |
実行方法 |
E-E-A-T区分 |
|
構成・表現の統一や最適化 |
論理的な構成になっているか確認する |
見出しの順序や情報の流れを整理し、AIが因果関係を誤解しない構造を整える。 |
- |
|
必要な話題を取捨選択しながら網羅する |
メインテーマの理解に必要な関連する話題をバランスよく含め、AIがトピック全体を正確に把握できるようにする。 |
- |
|
|
1つの見出しごとに問いと答えを用意する |
各H2・H3で読者の疑問を明示し、その答えを本文で簡潔に提示する。AIがQ&A形式として構造を把握しやすくなる。 |
- |
|
|
一次情報と信頼性の強化 |
自社で調査・入手した情報を掲載する |
自社で得たデータ・アンケート・事例などを一次情報として掲載し、AIが独自性の高い情報として引用しやすくする。 |
E |
|
E-E-A-Tを意識する |
経験・専門性・権威性・信頼性を示す情報を本文内に明記し、著者情報や出典を付与してAIが信頼できる情報源と判断できるようにする。 |
E、E、A、T |
|
|
情報を引用する場合は出典元を明記する |
政府・統計・専門機関などの出典を明示し、外部情報の正確性を担保する。AIが一次情報との関連性を正しく把握できるようにする。 |
T |
|
|
文章表現の最適化 |
結論から述べる |
段落の冒頭に要点・結論を提示し、AIが主張を先に把握できる構造を意識する。 |
- |
|
箇条書きや番号つきリストを活用する |
要素や手順などをリスト化し、AIが情報の構造や並列関係を明確に理解できるようにする。 |
- |
|
|
定義文やQ&A形式での書き方を取り入れる |
「〇〇とは〜である」の形式や「質問→回答」の形式を活用し、AIが意図を明確に抽出できるようにする。 |
- |
|
|
テクニカル面の最適化 |
正しいHTML構造でページを作成する |
H1→H2→H3→H4の見出し階層を守り、内容構造を明確化。AIが主題と小項目を正しく把握できるようにする。 |
- |
|
構造化マークアップを行う |
Article・FAQPageなどの構造化データを実装し、AIが文脈を機械的に理解できるようにする。 |
- |
|
|
ページ速度を最適化する |
表示速度を改善し、AIクローラーがページを正しく解析できる環境を整える。 |
- |
|
|
llms.txtを設置する |
ルートディレクトリ直下にllms.txtを設置し、AIに参照してほしいURLを指定する。 |
- |
自社名・ブランド名をAIに言及してもらう場合
自社名・ブランド名をAIに言及してもらうためには、自社の会社名をはじめとした会社情報や商品・サービスの内容を正しくAIに理解してもらう必要があります。
|
カテゴリ |
実施内容 |
実行方法 |
E-E-A-T区分 |
|
構成・表現の統一や最適化 |
論理的な構成になっているか確認する |
会社概要ページやサービス紹介ページの項目を整理し、AIが会社・サービスについて誤解しないようにする。 |
- |
|
必要な話題を取捨選択しながら網羅する |
会社紹介ページに、企業名・ブランド名・所在地・設立・主要サービス・代表者など、AIが会社概要を理解するために必要な情報を漏れなく掲載する。 |
- |
|
|
1つの見出しごとに問いと答えを用意する |
「株式会社〇〇とは?」「どんなサービスを提供している?」「他社との違いは?」など、質問形式で自社情報を整理し、AIがQ&Aとして認識しやすい構造を作る。 |
- |
|
|
一次情報と信頼性の強化 |
自社で調査・入手した情報を掲載する |
自社独自の調査データや顧客事例を会社紹介ページに掲載。AIが「一次情報の提供元=自社」として認識しやすくする。 |
E |
|
E-E-A-Tを意識する |
企業としての実績・経験年数・取引社数などを掲載し、AIに「専門性・実績のある組織」として理解される構造を整える。 |
E、E、A、T |
|
|
情報を引用する場合は出典元を明記する |
外部データや業界統計を参照する際は出典を記載し、AIが自社の主張の根拠を正しく把握できるようにする。 |
T |
|
|
文章表現の最適化 |
結論から述べる |
各ページ冒頭に「株式会社〇〇は〜を提供する〇〇サービスです」など記載し、AIが冒頭で自社の概要を把握できるようにする。 |
- |
|
箇条書きや番号つきリストを活用する |
自社の特長・強み・サービス内容をリスト化し、AIが自社情報を抽出・要約しやすい形式にする。 |
- |
|
|
定義文やQ&A形式での書き方を取り入れる |
「株式会社〇〇は△△を行っている」「株式会社〇〇どのような特徴があるか?」などの定義文や質問形式を採用し、AIが企業情報を明確に引用できるようにする。 |
- |
|
|
テクニカル面の最適化 |
正しいHTML構造でページを作成する |
自社名・ブランド名をH1またはH2見出しに含め、AIが「ページテーマ=企業情報」と理解できる構造にする。 |
- |
|
構造化マークアップを行う |
Organization構造化データを用いて、自社名・所在地・ロゴ・公式URLをマークアップする。 |
- |
|
|
ページ速度を最適化する |
表示速度を改善し、AIクローラーがページを正しく解析できる環境を整える。 |
- |
|
|
llms.txtを設置する |
ルートディレクトリ直下にllms.txtを設置し、AIに参照してほしいURLを指定する。 |
- |
LLMOの効果測定方法
ここまで、LLMOの実施方法や実際の実施例についてご紹介しました。LLMOに取り組んだ際は、どのくらい効果があったのか、改善点を見つけるうえでも効果測定を行いましょう。セッション数など各指標の確認方法は、以下のとおりです。
自社コンテンツへのAI経由でのセッション数
AIによる引用を経由して自社コンテンツにどのくらいアクセスされたのか、セッション数を調べる際は、Google アナリティクス(GA4)を利用することで確認できます。
GA4を使って自社コンテンツへのAI経由でのセッション数を調べる手順は、以下のとおりです。ここでは、Gemini経由でのセッション数を求める方法をご紹介します。
1.GA4で「探索」レポートを新規作成する

引用:GA4
2.「セグメント」横の「+」をクリックし、「新しいセグメントを作成」をクリックする

引用:GA4
3.「セッション セグメント」を選択する

引用:GA4
4.条件で「セッションの参照元 / メディア」を選び、「gemini.google.com / referral」を「含む」で定義を設定する

引用:GA4
AIによる自社コンテンツの採用回数
AIによる自社コンテンツの採用回数は、Ahrefsで確認できます。Ahrefsを使って自社コンテンツへのAI経由でのセッション数を調べる手順は、以下のとおりです。
1.Ahrefsの「Site Explorer」に自社サイトのURLを入力する
2.「AI 引用」の項目を確認する

引用:Ahrefs
なお、この機能はAhrefsの「ブランドレーダー」機能に含まれており、オプションとして追加できます。
AI Overviewで自社コンテンツが採用されたキーワードの抽出
Googleの検索結果に表示される「AI による概要(AI Overview)」で、どのようなキーワードが検索されたときに自社のコンテンツが採用されたのかを、Ahrefsで調べられます。
AI Overviewで自社コンテンツが採用されたキーワードの抽出方法は、以下のとおりです。
1.Ahrefsの「Site Explorer」に自社サイトのURLを入力する
2.左メニューの「オーガニックキーワード」をクリックする
3.「フィルタを追加」をクリックする

引用:Ahrefs
4.「SERP の機能」をクリックする

引用:Ahrefs
5.「AI Overview」を選択し、「承認」をクリックする

引用:Ahrefs
6.「表示結果」をクリックして、キーワードを確認する

引用:Ahrefs
改善サイクルを素早く回すコツ
LLMOでは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)のPDCAサイクルを素早く回すことが重要です。
初めに「〇〇のキーワードで検索された際に、〇〇という質問に対してAIから引用されるのではないか」などの仮説を立て、仮説を実現するために必要な要素を整理したうえでページ構造の修正や記事執筆などのLLMOを行います。
LLMOの実施後は、上記であげた方法で効果検証を行い、「仮説どおりの結果が得られたか」「成功点」「失敗点」などを分析します。あわせて改善点をまとめ、次回に向けた仮説立てや準備を行い、再度LLMOを行いましょう。
このようにPDCAサイクルを継続的に回すことによって、LLMOの効果が得られるだけでなく、SEOなどの評価が高まることも期待できます。LLMOによる自社サイトの認知度・アクセス数向上から問い合わせ・購入といったCVにつなげ、自社の売上アップまで狙えるよう、根気強く分析と改善を繰り返しましょう。
LLMO実施前に確認できるチェックリスト
ここまで、LLMOの実施方法や効果測定方法をご紹介しました。上記であげた通り、LLMOに取り組む際はさまざまな施策や効果測定を行う必要があるため、実施前に「準備がしっかりできているか不安」と感じる方も多いでしょう。
以下では、LLMOの実施時に役立つチェックリストをご紹介します。LLMOの施策を始める前に、ぜひこのチェックリストを活用して、必要な準備ができているかをご確認ください。
1.AIが理解しやすいページ構造
|
項目 |
内容 |
|
正しいHTML構造になっているか |
H1→H2→H3→H4の階層構造を守り、主題・小見出し・補足の関係を明確化できているか。 |
|
構造化マークアップを実装しているか |
Article、FAQPageを構造化データを実装し、AIが文脈を正しく理解できているか。 |
|
論理的な構成になっているか |
ページ全体が「結論→理由→詳細」の順で整理され、因果関係が明確になっているか。 |
|
ページ表示速度が最適化されているか |
ページ表示速度を改善し、AIが正しくページを解析できる状態になっているか。 |
|
llms.txtを設置しているか |
ルートディレクトリ直下にllms.txtを配置し、AIに参照してほしいURLを指定できているか。 |
2.AIが理解しやすい・引用しやすい文章構造
|
項目 |
内容 |
|
結論から述べているか |
各段落や見出しの冒頭で要点を提示し、AIが重要情報を先に把握できているか。 |
|
箇条書きや番号つきリストを活用しているか |
要素や手順をリスト形式で整理し、AIが並列関係・順序を理解しやすい構造になっているか。 |
|
定義文を使用しているか |
「〇〇とは〜である」など、AIが概念を正確に認識できる定義文を設けているか。 |
|
Q&A形式を取り入れているか |
「質問+回答」形式でコンテンツを構成し、AIがFAQとして抽出できる構造になっているか。 |
|
必要な話題を網羅できているか |
メインテーマの理解に必要な関連トピックを過不足なく盛り込み、AIが全体像を把握できているか。 |
|
問いと答えの対応が明確になっているか |
各見出しで読者の疑問を提示し、本文でその答えを簡潔に示せているか。 |
3.効果測定
|
項目 |
内容 |
|
AIでの引用状況を確認しているか |
ChatGPT・Geminiなどで自社コンテンツが引用・参照されているかを定期的に検証しているか。 |
|
サイテーションを把握できているか |
他サイトやニュースメディア、プレスリリースなどで自社URL・社名が言及されているかを確認できているか。 |
|
AI経由・検索経由の流入を分析しているか |
Ahrefsなどの解析ツールでAI経由・自然検索流入の変化を可視化できているか。 |
|
改善サイクルを回しているか |
ページ構造や文章の修正を定期的に行い、AI引用結果や分析データをもとに改善できているか。 |
4.運用体制
|
項目 |
内容 |
|
一次情報を発信できる体制があるか |
自社で調査・検証を行い、独自データを継続的に公開できる体制が整っているか。 |
|
E-E-A-Tを反映できる体制であるか |
専門性・経験・信頼性を担保するための執筆・監修・更新体制を確立しているか。 |
|
出典元の表記ルールを統一しているか |
外部情報の出典元を全記事で統一されたフォーマットで明記し、信頼性を担保できているか(出典元で個別の表記ルールがある場合を除く)。 |
|
HTML・構造化データを管理できているか |
CMSの管理者や開発チームと連携し、HTML構造・構造化データ・ページ速度などを継続的に最適化できているか。 |
|
改善フローが確立されているか |
LLMO施策の効果検証・改善を定期的に行う運用プロセスを確立できているか。 |
LLMO実施時の注意点
ここまで、LLMOを実施する際に活用できるチェックリストをご紹介しました。チェックリストに記載の内容はもちろん、LLMOの実施時には注意点も押さえておくとよいでしょう。
AIに引用されてもクリックされるとは限らない
LLMOを適切に行うことで、AIに自社コンテンツの内容を引用してもらえる可能性がありますが、必ずクリックされるわけではないことを念頭に置いておきましょう。
例えば、ChatGPTに「2025年のハロウィンイベントを教えてください」と質問した場合、以下のようにイベントをピックアップしてもらえますが、イベント名や開催日、会場、イベント内容はチャット上に簡単にまとめられるため、リンク先のページに飛ばずとも、ユーザーはイベントの概要を把握できます。

引用:ChatGPT
自社のコンテンツから情報が引用されたとしても、ユーザーが「AIとのチャット上で知りたい内容が知れたから満足」と感じ、リンク先をクリックしないケースもあるため、必ずしもクリック率や自社サイトへのアクセス数が増えるとは限らない点にご注意ください。
AIが誤った情報を掲載する恐れがある
AIの精度は常に向上しているものの、すべての回答内容が正しいとは限りません。たとえ事実のような書き方で回答していたとしても、実際は事実とは異なっている「ハルシネーション」を起こすことも少なくないため、ユーザーに自社の情報を誤って認識されてしまう可能性もあることに注意しましょう。
また、AIには「ナレッジカットオフ」と呼ばれる学習データの最終収集日があり、例えばChatGPTで使われているGPT-5は、2024年9月30日までの情報が蓄積されています。
そのため、2024年9月30日以降の情報は学習モデルが認識できていないため、現在は閉店している店舗を「営業中」と回答したり、古い会社住所や電話番号を回答したりする恐れがあります。
ChatGPTなどのAIはWeb上から情報を収集できるため、最新の情報も引用してもらえますが、ナレッジカットオフの期間と差が生じることによって誤った回答をする可能性もゼロではない点にご注意ください。
長期的に取り組むことが大切
LLMOは、短期的に成果が出にくく、長期的に継続して取り組むことが大切です。また、SEOのように検索順位やクリック率などの指標でわかりやすく効果を実感しにくい面もあるため、「取り組んだはいいものの成果が出ていないのではないか」と不安になるケースも少なくありません。
LLMOでは、コンテンツの専門性の高さや信頼性が評価されることでAIに取り上げてもらえます。このような専門性や信頼性はSEOやWeb集客においても重要で、自社サイトの評価を上げて集客効果を高めるうえでも必須の要素となるため、LLMOで成果が出ないからといってこれまでの施策をすぐに諦めるのではなく、自社の目的や目標に沿って根気強く取り組み続けることが大切です。
LLMOに関するよくある質問
ここまで、LLMOを実施する際の注意点をご紹介しました。LLMOに取り組むうえで、「事前に準備することはあるのか?」「llms.txtは必ず設置しなければならないのか?」など疑問が生じることもあるでしょう。ここでは、LLMOに関するよくある質問にお答えします。
LLMOを行う前に準備すべきことは?
LLMOを行う前には、自社が現在業界の中でどの立ち位置にあるのか、現状分析から行いましょう。現状分析は、以下の手順で行います。
1.ChatGPTなどのAIに、自社の業界・地域でおすすめの企業・ブランド・商品などを尋ねる
例:「東京でおすすめのSEOコンサルティング会社は?」「〇〇駅でおすすめの歯科医院を教えて」など
2.Gemini、Copilot などほかのAIにも同じ質問をする
3.以下の点を確認する
「自社名が出たか」「競合がどのくらいの頻度でAIに言及されていたか」「どのような情報に注目してピックアップしているか」
4.上記の内容をもとに、競合がピックアップされる理由や、自社の不足事項を考える
5.目標を設定する
例:「『〇〇駅でおすすめの美容室』と尋ねた際に自店舗が言及される確率を高める」「AI経由でのアクセスを増やす」など
llms.txtは必ず設置する必要がある?
llms.txtはLLMOの効果を高める可能性はあるものの、今すぐに設置しなければならないものではありません。
llms.txtは、2025年現在AIシステムには使用されておらず、llms.txtを設置したとしても確実にAIが情報を読み取ってくれるわけではない点に注意が必要です。
Google検索リレーションチームのリーダーであるJohn Mueller(ジョン・ミューラー)氏は、Blueskyにて「FWIW no AI system currently uses llms.txt.(ちなみに、現在AIシステムではllms.txtは使用されていません)」と述べています。
FWIW no AI system currently uses llms.txt.
— John Mueller (@johnmu.com) 2025年6月17日 21:10
中小企業でもLLMOは必要ですか?
サイトの規模に関わらず、AIに引用されることによって自社サイトの露出機会が増えるため、より多くのユーザーに自社サイトの存在を認知してもらえたり、サイトに訪れてもらえたりする可能性が高まります。
ただし、SEO対策やSNS運用、広告運用などそのほかのWebマーケティング施策もLLMOを始めるうえでは企業の信頼性を確保するうえで重要となるため、LLMOが必要なのか、そのほかの集客方法でもまだ伸びしろがあるのかを見極める必要があります。
LLMOをやるとCV率が向上する?
LLMOによってAIに自社のコンテンツや商品・サービスを取り上げてもらった場合、AI経由でユーザーが自社を認知し、興味を持ってくれる可能性があるため、間接的なCV向上が期待できます。
AIが示した自社サイトのリンクをユーザーがクリックしなかったとしても、後に自社の名前やブランド名、商品名などで検索(指名検索)をし、自社の商品やサービスを購入・問い合わせする可能性もあります。
サイトの形態によってLLMOの効果は変わる?
サイトの形態によって、LLMOの効果は大きく変わると考えられます。
例えば、自社の商品やサービスのブランドサイトやプロダクトサイトの場合、AIが自社の商品・サービス名やブランド名、会社名などをユーザーとのやりとりの中で言及する可能性が高いため、LLMOを行うことが推奨されます。
一方で、求人サイトなどのポータルサイトやデータベース型サイト、メディアサイトは、ユーザーがポータルサイト・データベース型サイト・メディアサイトそのものを探す可能性は低いため、このようにユーザーの目的を果たすための架け橋のような役割を担うサイトは、LLMOとの相性はあまりよくないと考えられます。
AIの引用から自社サイトに遷移する割合はどのくらい?
AIの引用から自社サイトに遷移する割合は、現時点ではそれほど大きくなく、0.1%未満だといわれています。
しかし、AIが回答し、自社の名前が言及されることで、興味を持ったユーザーが自らその企業名を検索し、詳細を調べる可能性はあります。そのため、AI経由での遷移率だけでなく、指名検索が増えているかなどもあわせて確認し、分析を行うとよいでしょう。
LLMOは外注できる?費用相場はどのくらい?
LLMOは、SEOコンサルティング会社やWeb集客コンサルティング会社に依頼でき、SEOなどとあわせてLLMOのサポートを行ってもらえます。
費用は取り組み内容やサイトの規模、実施期間によっても異なりますが、1カ月30万円程度が相場といえます。なお、施策の開始タイミングでは、月額費用のほかに別途初期費用が必要になる場合もあるため、ご注意ください。
まとめ
この記事では、LLMOとは何かを、SEOとの違いや実施するメリット、実際に取り組む際の具体的な方法、実施時の注意点などとあわせてご紹介しました。
LLMOを行い、AIに自社の情報を取り上げてもらうことで、自社の認知度やブランド価値の向上や、AI経由でのアクセス・CVを狙えるため、SEOなどのほかのWebマーケティング施策とあわせて取り組むのもよいでしょう。
しかし、LLMOはまだ比較的新しい手法であり、最適な施策が今後変化する可能性もあり、柔軟に対応していく必要があります。
当社のWeb集客サービス「バンソウ」では、SEOはもちろん、LLMOもサポートしています。「LLMOについてもっと詳しく知りたい」「自社でLLMOを取り組むべきか?」とお悩みの方は、ぜひ当社までご相談ください。
また、「今すぐ相談がしたい」という方に向けて、直接ご相談のスケジュールを予約できるフォームもご用意しています。ぜひ以下の予約フォームもご利用ください。


