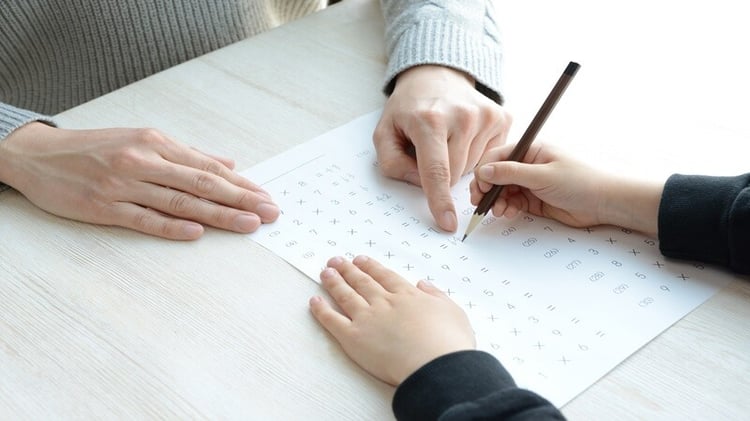SEOのトレンドとは?トレンドを意識したSEO対策についても紹介

SEOのトレンドは、移り変わりが早いため、常にアンテナを張っておく必要があります。
SEO対策といえば、主にGoogleに対して行うことから、Googleのコアアルゴリズムアップデートについては特に情報収集すべきだといえるでしょう。
この記事では、近年のSEOのトレンドの動向にはどのようなものがあるのかをご紹介します。
そのほかにも、トレンドを意識したSEO対策もご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
執筆者

マーケティングサポート「バンソウ」のメディア管理人
株式会社クリエイティブバンクのマーケティングサポート「バンソウ」のメディア管理人。得意分野は、SEO全般・サイト分析・オウンドメディア・コンテンツマーケティング。バンソウはクライアント様のBtoBマーケティングをサポートするサービスです。詳しい内容はこちらをご覧ください。
SEOのトレンドとは

SEOは、Googleが定期的に行うコアアルゴリズムアップデートの影響を強く受けることから、最新のアルゴリズムに対応した対策が必要です。
そのため、現在のSEOのトレンドについては把握しておくべきだといえるでしょう。
はじめに、近年のSEOのトレンドの動向についてご紹介します。
Webサイトの信頼性を高める
2022年に、Googleが公式にSEO対策に関する情報を発信している「Google 検索セントラル」に、「E-E-A-T と品質評価ガイドラインについて」という項目が追加されました。
E-E-A-Tとは、経験(Experience)、専門性(Expertise)、権威性(Authoritativeness)、信頼性(Trustworthiness)の頭文字を取ったもので、Googleがコンテンツの質を判断する際に用いる指標のひとつです。
すべてを満たす必要はないものの、組み合わせることでSEO評価を高められるとGoogleも述べています。
中でもGoogleは「信頼性」を重視していると述べていることから、信頼性を高めるようなコンテンツ作りが重要となっています。
個人ブログは「個人」の強みを生かす必要がある
E-E-A-Tで述べられている信頼性は、個人よりも大規模のWebサイトや知名度のある企業のほうが強くなってしまいます。
ただしGoogleは、2024年2月の時点でこのような知名度に関係なく、高品質なコンテンツが上位化されるように取り組んでいくとXにて明言しています。
Thank you. I appreciated the thoughtfulness of the post, and the concerns and the detail in it. I've passed it along to our Search team along with my thoughts that I'd like to see us do more to ensure we're showing a better diversity of results that does include both small and…
— Google SearchLiaison (@searchliaison) February 20, 2024
このことからもわかるように、高品質なコンテンツ作りは個人ブログであっても必須といえるでしょう。
その中で個人ブログだからこそできる強みを生かすことで、大規模なWebサイトや知名度の高い企業のWebサイトにも勝てる可能性があります。
自身の人脈を使って「京都在住〇年の友人おすすめのスポットを紹介」や、フットワークの軽さを生かして「秘境にあるカレー屋さんに行ってみた」など、個人だからこそ作りやすいコンテンツを考えてみましょう。
ショート動画の投稿がSEO対策になるケースもある
2023年から、Googleはスマートフォンで検索が行われた際に、検索結果にショート動画を表示させるようになりました。
ショート動画というタブが表示されるようになったほか、検索結果自体にも関連するショート動画が表示されるようになっています。
このような仕様になった理由として、近年ではTikTokをはじめ、YouTubeのショート動画やInstagramのリールなど、手軽に短時間で見られるショート動画が人気となっていることが考えられます。
そのため、キーワードによってはショート動画を作成して、検索結果に表示させるようにするのもSEO対策のひとつになるといえるでしょう。
サブディレクトリ貸しの低品質コンテンツが問題視されている
サブディレクトリ貸しとは、SEO評価の高いWebサイトのサブドメインやサブディレクトリを借りて、低品質なアフィリエイトコンテンツを上位化させる手法のことです。
ホスト貸しやサイト貸しのほか、寄生サイトなどと呼ばれることもあります。
2024年に、Googleは「Google ウェブ検索のスパムに関するポリシー」にサブディレクトリ貸しについて言及した「サイトの評判の不正使用」についての項目を追加しました。
言及されているように、大手無料ブログのようなサブドメインやサブディレクトリをユーザーが借りて使用するものもサブディレクトリ貸しに該当しますが、違反Webサイトに該当しているわけではありません。
問題視されているのは、E-E-A-Tを満たさない低品質なコンテンツが上位化されるケースがあることです。
サブディレクトリ貸しで低品質コンテンツを上位化させているWebサイトは、貸主と金銭的やりとりがあることも多く、ユーザーをだます行為でもあることから、ブラックハットSEOに該当するとの見方もあります。
AI Overviews(旧SGE)の普及によりゼロクリックサーチが増加する
AI Overviews(旧SGE・Search Generative Experience)とは、Googleの検索結果にAIが要約した文章を表示させる機能のことです。
AI Overviewsが普及することで、検索結果画面だけで必要な情報を取得できる機会が増えるため、Webサイトに訪れずに検索行動を終えるゼロクリックサーチが増加しているといわれています。
AIが要約する際に参照したWebサイトはAI Overviews内に表示されるため、参照サイトに選ばれるかどうかも、今後は重要になるのではという見方も強まっています。
参照:AI による概要 : ウェブにつながる新しい方法|Google
AI生成コンテンツのSEO評価は定まっていない
Googleは、「AI 生成コンテンツは Google 検索のガイドラインに抵触しますか?」という問いに対して「AI や自動化は、適切に使用している限りは Google のガイドラインの違反になりません」と述べているため、「Google ウェブ検索のスパムに関するポリシー」に抵触しなければ、AIでコンテンツを作成すること自体は問題ないといえるでしょう。
しかし、AIで生成したコンテンツは、オリジナリティのないありきたりなものになってしまい、そのままでは高品質とはいえないものがほとんどです。
さらに、ハルシネーションと呼ばれる誤った情報を含めて回答するケースもあるため、ファクトチェックを行わなければE-E-A-Tを満たせない可能性もあります。
SEOに強いコンテンツを作るためには、AIはあくまでもサポートツールとして使用するのがよいといえるかもしれません。
UAがGA4へと移行された
2023年7月1日に、Googleは解析ツールとして提供していたUA(ユニバーサル アナリティクス)の新規データ収集を停止しました。
そして2024年7月1日には既存データの閲覧も完全に終了し、GA4(Google Analytics 4)へと完全に移行しています。
GA4については、「GA4の初期設定手順とは?導入方法やはじめにすべき設定を含め詳しく解説」の記事で詳しく説明しておりますので、あわせてご覧ください。
GA4を使用する際には、Webサイトの掲載順位をモニタリングし、管理・改善するのに役立つGoogle Search Consoleの併用をおすすめします。
SEOトレンドを意識した対策とは

ここまで、近年のSEOのトレンドをご紹介しました。
AI技術の進歩により、AI Overviewsの導入やAI生成コンテンツについて言及されるなど、トレンドは変わっています。
ここからは、SEOトレンドを意識したSEO対策をご紹介します。
高品質なコンテンツを作成する
「Webサイトの専門性や信頼性を高める」でも述べたように、E-E-A-Tを意識したコンテンツ作りが質を高めるためには必須となります。
コンテンツ作成の際には、E-E-A-Tを念頭に置いて取り組みましょう。
E-E-A-Tの概要を含め、E-E-A-Tを高めるコンテンツ作りについて詳しく知りたい方は「E-E-A-T(E-A-T)とは?重要性や高めるコツを解説」の記事をご覧ください。
このほかにも高品質なコンテンツを作成するには以下の点が重要です。
独自性
E-E-A-Tのほかにも、オリジナリティもコンテンツの質を高めるひとつの要因になります。
独自で調査したアンケート結果や研究結果といった一次情報は価値が高いと見なされるため、積極的に取り入れることをおすすめします。
ページエクスペリエンス
高品質なコンテンツを提供することは、ユーザーがWebサイトを訪問することで体験できるページエクスペリエンスの向上にもつながります。
優れたエクスペリエンスを提供するWebサイトは、SEOで高評価を得られるとGoogleも明言しているため、高品質なコンテンツ作りはSEOにおいて重要といえるでしょう。
詳しくは「ページ エクスペリエンスの Google 検索結果への影響について」をご覧ください。
ユーザビリティを向上させる
ユーザビリティとは、ユーザー視点で見たWebサイトの見やすさや使いやすさを示す言葉です。
ユーザビリティを向上させると、先に述べたページエクスペリエンスも向上するため、SEO評価に関連する指標といえるでしょう。
ユーザビリティを向上させるためには、以下のような手法があります。
- レスポンシブデザインを導入するなどしてスマートフォンに対応させる
- Webサイトの読み込み速度を上昇させる
- Webサイトの構造を最適化する
タイトル・見出し・メタディスクリプションを設定する
コンテンツを作成する際には、タイトルと見出し、メタディスクリプションを設定しましょう。
HTMLの「titleタグ」「hタグ」「metadiscriptionタグ」を適切に設定することで、検索エンジンにもコンテンツの情報が伝わりやすくなり、正しいSEO評価を受けることにもつながります。
このほかにも、「linkタグ」や「imgタグ」などを設定することで、検索エンジンへ向けたWebサイトへのスムーズな理解を促せます。
これらを含めたHTMLタグについて詳しく知りたい方は、「SEOタグの設定方法とHTMLにおけるSEOの基本をわかりやすく解説」の記事をご覧ください。
404リダイレクトを設定する
404リダイレクトとは、削除されているページにユーザーがアクセスした際に、関連するページへリダイレクトする設定のことです。
この設定をしていない場合、ページが削除されていることを示す404エラー(404 not found)が表示されてしまいますが、404リダイレクトを設定することでエラーが表示されなくなり、ユーザーがエラーページから移動する際に操作が不要となるため、ユーザビリティの向上につながります。
XMLサイトマップを作成し送信する
Googleのような検索エンジンは、クローラーと呼ばれるロボットを巡回させることでWebサイトの情報を収集し、SEO評価をしています。
クローラーにWebサイトの構造をわかりやすく伝えるものがXMLサイトマップです。
XMLサイトマップを作成し、送信することでクローラーの巡回を促せます。
WordPressのようなCMSサービスを利用している場合は、プラグインを利用することで作成できるので、必要に応じて利用を検討してください。
サイトマップを作成したら、Google Search Consoleから送信しましょう。
noindexを設定する
noindexとは、HTMLコード内に記述するmetaタグの属性値です。
この値を記述することで、クローラーがWebサイトを巡回しインデックス登録することを避けられます。
noindexを設定するのは、以下のようなケースです。
- 重複するコンテンツがある
- 運営上の理由でリライトができない低品質なコンテンツ
- 特定のユーザーにしか公開しない限定コンテンツ
noindexの実装に関してはGoogleが公開している「noindex を使用してコンテンツをインデックスから除外する」をご覧ください。
AI Overviews(旧SGE)対策をする
SEOのトレンドでもご紹介したAI Overviewsは、Googleが導入している要約や関連情報の提供を強化するために設計された機能です。
2024年8月に日本でも展開されはじめたため、対策についてもこれから吟味されていくものといえます。
現時点でAI Overviews対策として有効とされているのは、先にご紹介したE-E-A-Tを満たした高品質なコンテンツを作ることです。
また、AIに参照されやすい構成でコンテンツを作成することも有効だとされています。
以下のような構成でコンテンツを作ることで、AIへの理解を促進できるでしょう。
- 結論を明確にする
- 目次を入れ、わかりやすい階層構造を作る
- ページ全体の要約がわかるセクションを作る
ここまで紹介した手法のほかにも、SEOのトレンドを問わず重要なSEO対策があります。
詳しい手法については、「SEO対策の種類とは?内部・外部対策の目的や主な施策を紹介
」の記事をご覧ください。
まとめ
この記事では、SEOトレンドについてご紹介しました。
SEO対策は、Googleが定期的に行うコアアルゴリズムアップデートの影響を強く受けることから、最新のアルゴリズムに対応する必要があります。
そのため、現在のSEOのトレンドを把握することは必須であるといえるでしょう。
SEOにトレンドはあるものの、高品質なコンテンツを作成したり、ユーザーが見やすいWebサイトにしたりすることは、トレンドの影響を受けづらい恒久的な施策だといえます。
この記事でご紹介したSEOトレンドを意識した対策も参考に、SEO対策へと取り組んでみてください。