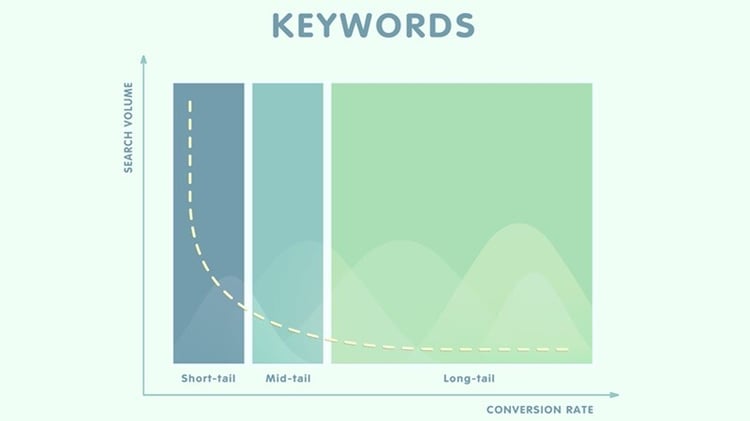メタディスクリプションが反映されないときの原因と対処法をご紹介!
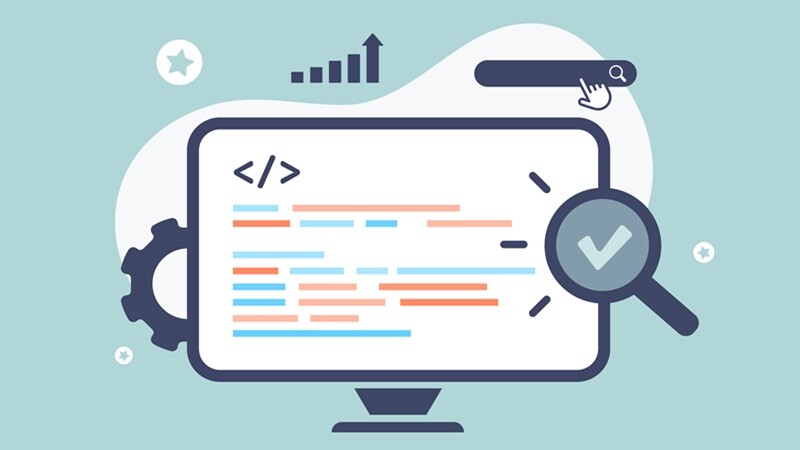
メタディスクリプションには、ユーザーに記事の内容をわかりやすく伝える役割があり、記事内容が伝わりやすいよう文章を作成し、関連性の高いキーワードを含めることで、検索結果に表示されやすくなり、Webサイトへの流入につながります。
そのため、ウェブサイト運営において、メタディスクリプションが検索結果に反映されないという問題は混乱を招くことがあります。
この記事では、メタディスクリプションが反映されない原因や対処法について詳しく解説するとともに、注意点や反映の確認方法についてもご紹介していますので、ぜひご参考にしてください。
執筆者

マーケティングサポート「バンソウ」のメディア管理人
株式会社クリエイティブバンクのマーケティングサポート「バンソウ」のメディア管理人。得意分野は、SEO全般・サイト分析・オウンドメディア・コンテンツマーケティング。バンソウはクライアント様のBtoBマーケティングをサポートするサービスです。詳しい内容はこちらをご覧ください。
メタディスクリプションの設定にお悩みの方へ
Webサイトへの流入を増やすには、ユーザーの目を引くキーワードを含めるなど
メタディスクリプションの最適化が必要です。バンソウでは、適切なキーワード選定・
サイト内部の最適化などのSEO支援を行っています。メタディスクリプションの設定や
Web集客にお悩みの方はお気軽にご相談ください。
ここでは、メタディスクリプションが反映されない原因についてご紹介します。
Googleが独自で生成している
Googleはページの内容を読み取り、設定したメタディスクリプションより適した文章を独自で生成することがあります。生成されたメタディスクリプションはページの内容と一致し、ユーザーに適切で有益な情報を提供します。
これは、メタディスクリプションが適切でない場合に起こります。ユーザーに理解しやすい自然な表現や適切なキーワードの使用、適切な文字数などを考慮することが重要です。
Googleが本文から抜粋している
Googleがスニペット(検索結果でタイトルの下に表示される短い説明文)を決定する際、ページ内のテキストを利用して適切なスニペットを抜粋することがあります。そのため、ページを適切に表現しているメタディスクリプションは採用されますが、そうでなければ使われない場合もあります。
スニペットの内容を手動で変更することはできません。Googleは常に関連性の高いものを提供しようとするため、ニーズに合ったメタディスクリプションを設定しましょう。
プラグインとテーマが干渉している
WordPressの場合、テーマとプラグインの役割が重複してしまい、互いに干渉している可能性があります。テーマの中には、SEO対策のための機能が組み込まれているものがあり、SEO対策用のプラグインを導入しなくても十分に対策できることがあります。
しかし、そこにSEO対策用のプラグインをインストールしてしまうと、メタディスクリプションの設定などの機能の重複が生じ、メタディスクリプションが反映されないなどの問題が起こることがあります。
メタディスクリプションが反映されないときの対処法
ここでは、メタディスクリプションが反映されないときの対処法についてご紹介します。
ページとディスクリプションの内容が合っているか確認する
Googleによって自動的にメタディスクリプションを書き換えられてしまう場合、ページの内容とメタディスクリプションが一致しているかを確認してみましょう。
具体的には、以下のポイントをチェックします。
- メタディスクリプションがページのメイントピックを適切に説明しているか
- 不自然にキーワードを詰め込んでいないか
- 適切な文字数で設定されているか
これによって、Googleに自動でメタディスクリプションを変えられてしまう可能性を低減し、意図したスニペットをユーザーに届けることが期待できます。
文字数を調整する
設定したメタディスクリプションが反映されない場合は、メタディスクリプションの文字数を調整することも有効です。一般的に、最適な文字数は120字前後です。文字数が少なすぎたり多すぎたりすると、書き換えられる可能性があるため、文字数を調整して再度設定することで、検索結果に反映されやすくなります。
メタディスクリプションを書き直す
メタディスクリプションを書き直すことも効果的です。コンテンツを閲覧する人がどのようなキーワードで検索するかを考慮し、メタディスクリプションを適切に調整しましょう。書き直した後は、検索エンジンのクローラーがサイトを巡回して更新を確認します。これにより、設定したメタディスクリプションの反映が期待できます。
data-nosnippet属性を指定する
スニペットに表示される箇所にHTMLのdata-nosnippet属性を設定することで、その部分はスニペットとして表示されなくなり、ページ内のほかの部分からスニペットが生成されます。もし、設定したディスクリプションの内容がほかの部分よりも適切だと判断されれば、その部分がスニペットとして採用される可能性があります。
テーマヘッダー(header.php)を確認する
プラグインをテーマの干渉を防ぐには、WordPressのサイドメニューにある「外観」から「テーマエディター」を開き、テーマファイル内の「テーマヘッダー」部分にある<meta name="description" content="○○(ディスクリプションの内容)">のコード(記述)を削除してみましょう。
ただし、削除する前には元に戻せるよう、必ずバックアップを取っておくことが重要です。コードの削除後はすぐ検索結果に反映されるわけではないため、しばらく時間がかかることを認識しておきましょう。
メタディスクリプションの反映に関する注意点
ここでは、メタディスクリプションの反映に関する注意点についてご紹介します。
反映には時間がかかることがある
メタディスクリプションを設定した後、すぐに検索結果に反映されることは少ないです。これは、クローラーがメタディスクリプションを更新したページを巡回し、検索エンジンのデータベースや検索結果の表示を更新するまでに時間がかかるためです。
反映を早くするためには、RSSフィードやXMLサイトマップをGoogle Search Consoleに登録し、記事を更新した際はインデックス登録をリクエストしましょう。これにより、検索エンジンに対してウェブサイトのコンテンツが更新されたことを効果的に通知し、反映を促せます。
更新頻度が低いとクロールの優先度が下がる
クローラーはインターネット上の情報を効率的に処理するために、更新頻度が低いサイトのページの巡回を減らす傾向があります。変更内容が反映されるまでには2〜3週間程度の時間がかかることもあります。それ以上時間がたっても反映されない場合は、更新のミスやメタディスクリプションの内容が適切でない可能性が考えられます。
スニペットは検索されるクエリによって変わる
スニペットの内容は、検索されるクエリ(ユーザーが検索するときに入力するワード)によって変化します。つまり、クエリAではメタディスクリプションの内容が表示されるかもしれませんが、クエリBではページ内の特定のコンテンツが表示される場合もあります。
そのため、スニペットの表示内容を調整する場合は、最も重要なクエリに対して調整を行うことが重要です。検索者が最も関心を持つであろうクエリに対して、適切なメタディスクリプションを提供することが、スニペットの改善につながります。
メタディスクリプションの反映を確認する方法
ここでは、メタディスクリプションの反映を確認する方法についてご紹介します。
「TITLE & META情報抽出」を使って確認する
メタディスクリプションの確認は、ラッコツールズが提供している「TITLE & META情報抽出」を使って行えます。やり方は、確認したいページのURLをラッコツールズの入力欄に入力し、「抽出」をクリックするだけです。すると、そのページで設定されているタイトルやメタディスクリプションなどがすぐに表示されます。
HTMLソースから確認する
メタディスクリプションが設定されているか確認する手段のひとつとして、ウェブページのHTMLソースから直接確認する方法があります。Google Chromeを使用している場合は、対象のページで右クリックし、「ページのソースを表示」を選択します。表示されたソースコードから、<meta name="description" content="○○(ディスクリプションの内容)">の部分を探します。
「content="○○"」に文章が記述されていなければ、そのページにはメタディスクリプションが設定されていないと考えられます。
まとめ
この記事では、メタディスクリプションが検索結果に反映されない問題についてご紹介しました。Googleのアルゴリズムやプラグインが原因となって、メタディスクリプションが正しく表示されないことがあります。しかし、更新頻度や内容の適切さを考慮し、適切なメタディスクリプションを設定することで、検索結果の表示改善が期待できるでしょう。