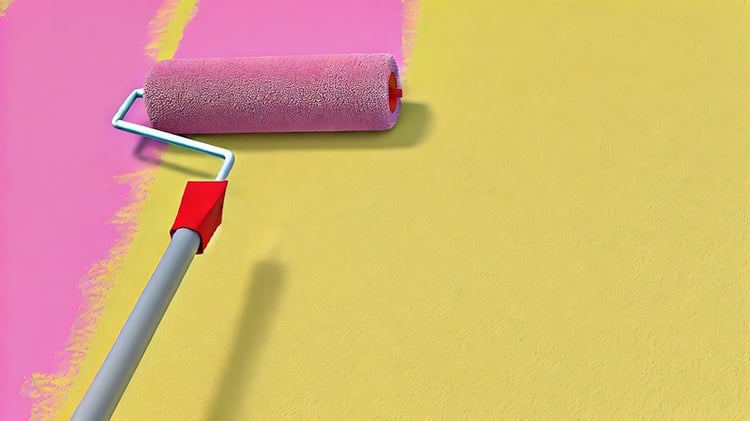不動産集客ができない理由は?最適な集客方法や見直すべき点を紹介

「広告費はかけているのに、反響が来ない…」
「ポータルサイトに掲載しているのに、なぜ問い合わせが減っている?」
そんな疑問や焦りを感じている不動産会社の方も多いのではないでしょうか。
人口減少・住宅ニーズの多様化・ネットを活用するユーザーの増加。今の不動産業界では、従来通りの集客方法では通用しない時代になっています。集客が思うようにいかない理由は、マーケットのせいだけではなく、「伝え方」や「仕組み」の問題かもしれません。
この記事では、不動産集客ができない根本原因と、成果につながる具体的な集客手法をわかりやすくご紹介します。改善のヒントを探している方にとって、必ず役立つ内容となっていますので、ぜひ最後までお読みください。
執筆者

マーケティングサポート「バンソウ」のメディア管理人
株式会社クリエイティブバンクのマーケティングサポート「バンソウ」のメディア管理人。得意分野は、SEO全般・サイト分析・オウンドメディア・コンテンツマーケティング。バンソウはクライアント様のBtoBマーケティングをサポートするサービスです。詳しい内容はこちらをご覧ください。
Web集客の課題を今すぐ相談したい方へ
「もう時間がない」「広告費だけが減っていく」そんな課題を抱えている不動産会社様へ。
Web集客に強い不動産向け支援サービスをご活用ください。
最短で反響を獲得するための仕組み作りを、無料でご相談いただけます。
反響が来ない…不動産会社が抱える集客の悩みとは?

「昔はもっと問い合わせが多かったのに」「最近、ポータルサイト経由の反響が明らかに減ってきた」そんな声が、不動産業界の現場では数多く聞かれます。
反響数が減ると、営業の機会そのものが減少し、売上の見通しにも直結します。
しかも、広告費はかかり続けているのに結果が伴わない状況では、焦りや不安が膨らむばかり。ここでは、実際の現場で多くの方が抱えている代表的な悩みを整理してみましょう。
問い合わせが減った・来店が少ないと感じている
最近、ホームページやポータルサイトを通じた「資料請求」「内見予約」「来店相談」などの具体的なアクション数が減っていると感じていませんか?
原因は「市場が冷えている」だけではありません。情報の伝え方や見せ方が、ユーザーのニーズに合っていない可能性があります。
広告を出しても費用対効果が合わない
チラシ・ポスティング・検索連動型広告など、広告出稿をしても、「広告費ばかりかかって、反響が見合わない」と感じるケースは非常に多いです。
その背景には、「ターゲットとのズレ」や「魅力の伝えきれていないクリエイティブ」など、広告の“中身”の課題が潜んでいることも少なくありません。
ポータルサイトに掲載しても差別化できない
SUUMOやHOME'Sなどのポータルサイトは、確かにユーザーの流入が多い反面、同じエリア・同じ価格帯の物件が並び、埋もれやすいという欠点もあります。
物件情報の羅列だけでは他社との差別化が難しく、“選ばれる理由”を見せられないままスルーされてしまう状況が起こりがちです。
地域の競合に埋もれてしまう
都市部・駅近など、競合が多いエリアでは「地元密着で30年」といった強みもなかなか目立ちません。Webでの比較が当たり前になった今は、ユーザーが「この会社に聞いてみたい」と思えるかどうかがすべて。
発信力と見せ方の工夫がなければ、良い物件を抱えていても、そもそも選ばれるきっかけを得られないのです。
なぜ不動産集客ができないのか?業界における5つの原因

広告費をかけても反響が伸びないのは、単に「運が悪い」「景気が悪い」という問題ではありません。根本的な要因が社内に潜んでいることも多く、実は改善できるポイントが見逃されているケースが少なくありません。
ここでは、不動産会社が陥りやすい集客停滞の代表的な5つの原因を解説します。
人口減少による市場の縮小
少子高齢化・単身世帯の増加など、日本全体での住宅ニーズの変化と人口の減少は避けて通れない現実です。とくに地方都市では、「住み手」そのものが減っており、供給側の数がニーズを上回ってしまう状態が顕著になっています。
この構造変化を正しく認識し、ただ物件を紹介するだけではなく、“選ばれるための提案”ができるかが、今後の集客の明暗を分けます。
ターゲットと訴求がズレている
「この物件、よいはずなのに選ばれない」それは、ターゲットと物件特性のミスマッチが原因かもしれません。
例えば、若年層向けに打ち出しているのに家賃が高すぎたり、子育て層向けと謳っていながら周辺施設の情報が薄かったり。また、複数社が似たような物件を掲載している中で、「ここならでは」の強みが見えていないと、選ばれずにスルーされがちです。
ユーザーの意思決定プロセスの変化
現代のユーザーは、来店前に「比較検討を終えている」ことがほとんどです。Google検索、SNS、口コミ、ポータルサイトなどから多くの情報を集め、「この会社なら安心」「この物件に問い合わせてみたい」と判断してから動き出します。
つまり、リアルな営業トークではなく、“ネット上での情報設計”が意思決定に直結する時代。この意識が抜けていると、知らない間に競合にリードを奪われている可能性があります。
Webサイトやポータル内での導線が弱い
問い合わせフォームの場所が分かりにくい、次のステップ(内見・資料請求・LINE予約など)への導線が不自然、最新情報が掲載されていない。こうしたちょっとしたWeb上の不親切が、ユーザーの離脱を引き起こしてしまいます。
特に物件ページの情報更新が滞っていると、「ここは対応が遅いかも…」という印象につながり、信頼を損ねる要因にもなります。ユーザーが迷わず、ストレスなく次の行動に移れる設計が求められます。
アナログ集客への依存が続いている
チラシ・看板・店頭対応など、従来のアナログ手法に頼りきりの状態では、現代のユーザーにリーチできません。特に若年層や共働き世帯は、「スマホで調べて、ネットで完結する流れ」に慣れています。
時間のないユーザーは、わざわざ店舗に来る前に判断を終えているので、時代に合ったオンライン施策を取り入れることで、費用対効果の高い集客が実現できます。
不動産業界でも「Web集客」が不可欠な理由

かつては駅前店舗の立地や、折込チラシの配布量が集客のカギでした。しかし今、上記で説明したとおり、物件を探すユーザーの多くが「ネットで検索」する時代になっています。
「ネットで探す」ことが当たり前になった今、不動産業界においてもWeb集客を戦略的に活用できるかどうかが、反響数・来店数・成約数に大きく影響しています。ここではその理由を、4つの視点から解説します。
ユーザーの多くがネット検索から物件を探す
「〇〇駅 賃貸」「ファミリー向け マンション 〇〇市」など、具体的な検索キーワードを使って物件を探すユーザーが圧倒的に増えています。特に20代〜40代の層は、まずGoogleで検索し、ポータルサイトや不動産会社の公式サイトを見て情報を集めるのが基本動作です。
つまり、検索結果に出てこない不動産会社=“存在していない”も同然。見つけてもらえなければ、いくらよい物件を抱えていても選ばれることはありません。
SNSや口コミで情報が拡散されやすい
InstagramやTikTok、X(旧Twitter)などのSNSは、今や“生活の一部”です。
内見に行った感想や対応の印象など、ユーザーが感じたことを投稿・共有することで、企業や店舗のイメージが自然に拡散される時代です。
また、Googleマップやポータルサイトの口コミも意思決定に直結します。丁寧な接客、誠実な対応、地域密着の強みを持っているなら、それをSNSや口コミで“じわじわ広げていく”ことが、広告以上の効果を生むこともあります。
問い合わせ前に信頼関係を構築できる
ユーザーは、「どんな会社なのか」「スタッフの雰囲気は?」「この会社に任せて大丈夫か?」を事前にチェックしています。公式サイトやブログ、SNSなどで発信している情報の質と量が、そのまま信頼の判断基準になるのです。
例えば、「購入体験談」や「物件選びのコツ」など、役立つ情報を発信していれば、「ここは親切そう」「相談してみようかな」と思ってもらいやすくなります。問い合わせ前に“好印象”を先に作っておくことが、現代のWeb集客では極めて重要です。
データを活用した反響営業や分析が可能になる
Web施策の大きな強みは、すべてが“数値で見える化できる”ことです。「どのページがよく見られているか」「どんなキーワードで流入しているか」「どこで離脱しているか」などを分析すれば、反響を増やすための改善が的確に行えます。
さらに、どの広告が効果的だったか、反響単価はいくらかなども把握できるため、費用対効果の高い施策に集中することができます。「なんとなく集客する」時代は終わり、“根拠ある集客戦略”が求められる時代に入っているのです。
Web集客をはじめてみませんか?
「Webからの問い合わせが増えない」「SEOに取り組んでいるのに成果が出ない」
そんなお悩みありませんか?
バンソウは、企業規模や業界問わず、SEOを活用した
Web集客の仕組み化を支援しています。
キーワード設計から記事構成、コンテンツ制作、改善提案まで――
戦略から実行までをまるっとおまかせできるのが、バンソウの強みです。
特別なツールやシステム導入は不要。
社内のリソース不足に悩む企業様でも、最短1カ月で施策をスタートできます。
まだ本格的にWeb施策を始めていない企業様でもご安心ください。
プロの編集・SEOチームが貴社のビジネスに合わせた集客戦略を伴走型でサポートします。
集客の成果を出すために押さえるべき3つのポイント

Web集客の重要性は理解していても、「実際にどう動けばいいのかわからない」という声も多く聞かれます。ここでは、反響数や成約率を高めていくうえで、今すぐ見直すべき3つのポイントをご紹介します。
他社との違いを明確にし、ターゲットに伝える
「どこも似たような物件ばかり」「結局どの会社も同じに見える」そう思われてしまえば、いくら魅力的な物件を扱っていても、選ばれることはありません。
差別化のカギは、“誰にとって何が強みなのか”を明確に打ち出すこと。例えば、「ファミリー層向けの駐車場付き物件が豊富」「学生専用マンションに強い」「ペット可・デザイナーズ物件に特化」といったように、具体的なターゲット層と、その人が重視する条件を踏まえた打ち出しが効果的です。
競合が多い地域でこそ、「この会社に聞いてみよう」と思わせる“軸”が必要です。
想定顧客像に合わせた訴求・接触チャネルを選ぶ
「若年層にはInstagramやLINE」「ファミリー層にはSEOや地域ブログ」「高齢者には紙媒体や電話対応」といったように、ターゲットごとに“見るメディア”“信頼する情報源”は異なります。
すべての媒体で平均的に出すよりも、想定顧客の行動や関心に合わせて情報発信のチャンネルを絞る・最適化することで、費用対効果は大きく改善できます。
特に見落とされがちなのが、広告文やコンテンツの“語り口”。「駅チカ」「設備が充実」といった無難なワードだけでなく、「小さな子どもが安心して暮らせる静かな立地」など、具体的なイメージが湧く言葉が刺さりやすくなります。
内見・資料請求など「次のアクション」への誘導設計を見直す
いくらよい情報を発信していても、「次にどう動いてほしいか」が曖昧だと、ユーザーは離脱してしまいます。例えば、「まずはLINEで気軽にご相談ください」「この物件が気になる方は、3分で終わる内見予約フォームへ」「資料をダウンロードした方には、非公開物件もご案内可能」など、次のステップを明確に提示し、行動のハードルを下げることが大切です。
また、内見予約や問い合わせフォームは、「入力項目が多すぎる」「スマホで見にくい」といった理由で離脱されることも多いため、UX(ユーザー体験)を意識した設計も欠かせません。
不動産業界でおすすめのオンライン集客方法

オンライン集客といっても、やみくもに始めるのではなく、「目的」と「対象ユーザー」に応じた施策の選定と組み合わせ」が成果の分かれ目になります。ここでは、不動産業界において即効性と持続性のある6つの施策を、実践のヒントとともにご紹介します。
自社ホームページの強化(SEO・CV設計)
ホームページは単なる「会社案内」ではなく、“集客拠点”として機能すべきツールです。まず見直すべきは、検索に強い構造(SEO)と、問い合わせにつなげる導線(CV設計)です。
- 物件ページごとのキーワード対策
- 「初めての家探しガイド」「エリア情報」などの集客コンテンツ
- スマホでも使いやすい内見予約フォーム
などを整えることで、「検索→閲覧→問い合わせ」という自然な流れを作り出せます。
ブログによる情報発信と検索流入獲得
自社ホームページ内でブログを更新することは、SEO対策と信頼構築の両面で非常に効果的です。「家賃相場の変化」「エリア別おすすめ物件特集」「失敗しない物件選びのコツ」など、ユーザーの不安や疑問に答える記事は検索にも強く、長期的にアクセスを集めます。
また、定期的な発信を通じて「この会社、情報発信がしっかりしていて信頼できるな」という印象も与えることができます。
ポータルサイトとの役割分担と差別化
SUUMO・HOME'Sなどの大手ポータルサイトは、集客チャネルとして優れていますが、競合との比較もされやすい場所です。だからこそ、ポータルは“集客入口”と割り切り、「自社の強みを伝える場」としては公式サイトやLINEなどへ誘導する導線設計が鍵になります。
たとえば、ポータル掲載文の末尾に「詳細は公式ページで」「非公開情報はLINEでご案内」などの導線を設けることで、“集めたアクセスを自社の資産に変える”工夫が必要です。
Googleビジネスプロフィールで地元対策
地域密着型の不動産会社にとって、Googleマップ検索対策(ローカルSEO)は非常に重要です。「〇〇駅 賃貸」「〇〇市 中古マンション」などの検索に対し、マップ上に表示される位置・情報の整備次第で、来店数・問い合わせ数が大きく変わります。
- 正確な営業時間・写真の登録
- 口コミへの返信
- よくある質問の追加
など、店舗の魅力や誠実さが伝わる情報管理が鍵となります。
SNS(Instagram・LINE・YouTubeなど)による接点づくり
SNSは物件を見せるだけでなく、“会社の雰囲気”や“人柄”を伝える場としても効果的です。例えば、Instagram・LINE・YouTubeでは、以下のような接点の作り方がおすすめです。
- Instagram → 内装・街並み・ライフスタイル提案
- LINE → 物件紹介や予約・やりとりの窓口
- YouTube → 物件紹介・ルームツアー・社内紹介動画
こうしたツールを通じて、ユーザーとの距離を縮め、問い合わせのハードルを下げていくことが可能です。特に若年層向けには、“売り込み感ゼロ”の自然な発信が好印象に繋がります。
不動産業界でおすすめのオフライン集客方法

Web集客が主流となる中でも、地元住民との信頼関係構築やシニア層へのアプローチには、オフライン施策が今も有効です。とくに、地域密着で長く営業している不動産会社であれば、“地元の顔”としての存在感を活かした集客方法が強みになります。
ここでは、オンライン施策と組み合わせることで相乗効果を生む、オフライン施策の代表例をご紹介します。
地域のフリーペーパー・チラシ
地元のスーパーマーケット、美容室、飲食店などに設置されているフリーペーパーや情報誌は、一定の年齢層に根強い訴求力があります。また、ポスト投函型のチラシも、「たまたま見た」から「問い合わせに繋がった」というケースが今でも少なくありません。
チラシにおいて重要なのは、地域ならではの訴求と限定感。
- 「〇〇小学校エリアのファミリー向け物件特集」
- 「このチラシ持参で仲介手数料10%オフ」
例えば、上記のようなターゲットに刺さるコピーと“地域とのつながり”を打ち出す工夫が効果的です。
商店街や地域イベントとの連携
商店街の夏祭り、地域の防災訓練、マルシェや子ども向けイベントなど、地元で開催される催しに参加・協賛することで、「あの不動産会社さん、よく見かけるよね」という認知と親近感を生み出すことができます。
とくに地域密着型の不動産会社は、顔の見える接点をつくることが信頼に直結します。パンフレットや名刺を配布するだけでなく、「空き家相談コーナー」や「簡易査定体験ブース」など、ちょっと立ち寄ってみたくなる仕掛けを作ると接点が生まれやすくなります。
店舗看板・のぼりなどの視認性向上
日常的に前を通る人の目に“自然に入る”店舗作りは、オフラインならではのブランディング効果があります。特に住宅街や駅前など、生活動線上に店舗がある場合は、看板やのぼり、外観の印象が非常に重要です。
「この前通ったときに気になっていたんです」と言われる来店動機は、まさに“視認性が集客につながった”好例です。
- 店名・営業内容が一目でわかる大きな看板
- 季節ごとに変えるキャッチ入りののぼり
- 夜間でも見える照明看板
など、視覚的アピールを継続して行うことが“無言の広告”として機能します。
集客に行き詰まったら、まず見直すべきポイント

ここまで、オンライン・オフラインのさまざまな集客方法をご紹介してきましたが、「何をやってもうまくいかない」「そもそも何が問題なのか分からない」そんな風に感じている方もいらっしゃるかもしれません。
集客が行き詰まったときは、小手先のテクニックを探す前に、根本の考え方や設計を見直すことが大切です。以下の3つの視点から、自社の集客活動を再点検してみましょう。
ターゲット像と訴求軸がズレていないか?
「どんな人に来てほしいのか」が曖昧なままでは、訴求の方向性もブレてしまいます。たとえば、“子育て世代向けの戸建て”を売りたいのに、訴求ポイントが“駅チカ”“単身者向け”になっている…というようなズレがないか確認してみましょう。
また、同じ物件でも「誰に、どんな価値を伝えるのか?」で広告の見え方は大きく変わります。具体的なターゲット像(年齢・家族構成・ライフスタイル)を想定し、それに合わせた打ち出し方を意識しましょう。
情報発信が「誰に、何を、なぜ伝えるか」を明確にしているか?
物件情報やブログ、SNSの投稿など、発信している情報が“自己満足”になっていないかを振り返ってみてください。「その情報は、誰のために、何の価値を届けるために発信しているのか?」この軸がないままでは、どれだけ発信しても響かず、反響にはつながりません。
特に、“なぜこの会社を選ぶべきか”が伝わる内容になっているか?は、不動産業界において非常に重要です。ユーザーの不安や疑問を先回りして解消するような発信を心がけましょう。
専門家に任せた方が早く解決できる場合もある
社内で集客改善に取り組むことは大切ですが、“何から手をつければいいか分からない”状態が長引くと、時間も広告費も無駄になってしまう恐れがあります。そんなときは、業界に精通した専門家の視点を取り入れることで、短期間で効果的な打ち手を見つけられる場合もあります。
たとえば、「ポータルだけに頼らない集客設計」「Webサイトの改善点診断」「広告出稿の最適化提案」など、第三者ならではの客観的視点での支援が、成果に直結することも多々あります。
バンソウの不動産業界に強いWeb集客支援サービス
バンソウでは、不動産業界の集客課題に特化したWebマーケティング支援を行っています。ただのSEO・広告提案ではなく、業界の特性に合わせた“成果が出る仕組み”をご提案いたします。
「問い合わせ数を増やしたい」「ホームページを改善したい」「競合に勝てる施策がほしい」そんなお悩みがある方は、ぜひお気軽にご相談ください。
まとめ
不動産業界では、人口減少やユーザーの行動変化により、従来どおりの集客手法では通用しなくなってきています。「反響が来ない」「広告が効かない」と感じているのは、あなただけではありません。
この記事では、不動産集客ができない原因から、オンライン・オフラインの具体的な施策、改善のためのチェックポイントまでを網羅的にご紹介しました。重要なのは、ターゲットに“きちんと届く伝え方”と“行動につなげる設計”を再構築することです。
今すぐすべてを変える必要はありません。まずはできるところから一歩ずつ改善していきましょう。「自社だけでは難しい」と感じたときは、ぜひ私たちのような専門家にご相談ください。